抗生物質 こうせいぶっしつ antibiotic
〈微生物によってつくられ,微生物の発育を阻止する物質〉
を antibiotic
と呼ぶことを,アメリカのラトガス大学教授
S.A.ワクスマン
が 1941 年に提唱した。日本では,これに
〈抗生物質〉
という語をあてている。 1929 年の A.フレミングによるペニシリンの発見,
38 年から 41 年にかけての H.W.フローリーらによる
〈ペニシリンの再発見〉
以降,新しい抗生物質の探索が世界的に始まった。したがって,抗生物質という言葉も物質も比較的新しいものである。
40
年以降,ストレプトマイシン,クロラムフェニコール,テトラサイクリンなどのすぐれた抗菌力をもつ抗生物質がつぎつぎに発見され,細菌感染症の治療は飛躍的に進歩した。その後のたゆまぬ新抗生物質の発見とその改良により,不感受性菌や耐性菌の問題もほとんど克服され,長い間恐れられてきた種々の伝染病
(結核,赤痢,腸チフスなど)
の重圧から人類は解放された。今日では,抗生物質の用途は,ヒトや家畜の医薬品としてのみならず,農薬や発育促進を目的とした家畜飼料添加など広くなっている。ワクスマンが提唱した抗生物質の定義は現在では狭義のものとなり,現在の概念からみれば,ワクスマンのそれは抗菌性抗生物質といえる。その後の抗生物質の発展により,制癌
(抗腫瘍) 抗生物質や抗ウイルス抗生物質も出現し大きな比重を占めるようになった。したがって現在では,抗生物質は
〈微生物によってつくられ,微生物その他の細胞の発育または機能を阻止する物質をいう〉
という概念のもとに用いられている。なお,高等植物および動物の組織から得られる同様の作用をもつ物質を抗生物質に含める場合もある。また,微生物がつくる物質のなかには,抗菌作用を示さず,酵素阻害作用や特異的薬理作用をもつ物質も見いだされ,医薬品としての有効性が追求されている。これらの物質は,生産する微生物の生育に必須ではないという意味で,
〈微生物の二次代謝産物〉
と呼ばれ, 抗生物質もそのなかの一部と考えられるようになっている。このように抗生物質の概念の変遷は,微生物を利用する学問研究の進歩をそのまま物語っているといえよう。
現在までに発見された抗生物質の数は
4000 を超え, 3 万以上の誘導体がつくられ,50
以上のものが臨床的に使用されている。日本は,昔から発酵技術
(酒,みそ,しょうゆ等) が進んでいるため, 抗生物質の分野でも世界的水準を保ち,
抗生物質生産は医薬品のなかでも上位を占めている
(
1994 年日本の医薬品の生産高 5 兆 7500 億円のうち抗生物質は約
4000 億円
)。 抗生物質の発見により,人類ははじめて細菌,リケッチア感染症を克服し,癌治療においても,まだ不十分ながら抗腫瘍抗生物質は大きな役割をはたし,今後とも期待が寄せられている。抗カビ,抗ウイルスまた新しい薬理作用をもった抗生物質,微生物生産物の開発も現在なお続けられ,
抗生物質は人類の健康に貢献することきわめて大なるものがある。
【抗生物質の発見史】
2
種の微生物を同時に培養した場合に,一方の微生物の発育が阻止されることを
拮抗現象
antagonism と呼ぶが,拮抗現象の研究は
J.ティンダル
(1876),
パスツール
(1877) に始まるといわれている。 1900
年に入って,何人もが拮抗現象を有する物質を抽出し,
ミコフェノール酸
などが報告されたが,医薬品としての利用は考えられていなかった。
28 年
A.フレミング
が偶然に
ペニシリン
を発見した。ブドウ球菌を培養した寒天培地の上にアオカビの
1 種
Penicillium notatum
が入り込み,アオカビが生えたまわりにはブドウ球菌は生えていなかったのである。しかし,アオカビの培養液中から強い抗菌作用で低い毒性の物質を抽出し,それをペニシリンと名づけたときも,医薬品としての応用は考えられなかった。
抗生物質の研究は,38
年ころからペニシリンの純粋分離の研究に着手したイギリスの
H.W.フローリー, E.B.チェーンの
〈
ペニシリンの再発見
〉
に始まる。これにより,微生物が生産する物質のなかには強力な抗菌作用をもつものが存在し,その物質が治療薬になりうるという指導原理が生まれたのである。
39 年
R.J.デュボス
は,バチルス菌Bacillus brevisの培養液からグラム陽性細菌の増殖を阻止する物質を結晶として分離し,
チロトリシン
(のちにグラミシジンとチロシジンの 2
物質に分けられた) と名づけた。 39 年からの 20
年間は抗生物質の黄金時代であり,つぎつぎと新物質が発見された。
ストレプトマイシン
(1944)
に続いて,細菌ばかりでなくリケッチアと大型ウイルスにも作用する
クロラムフェニコール
(1945),クロルテトラサイクリン (1948),オキシテトラサイクリン
(1950) が発見された。これらは広範囲スペクトル抗生物質であり,適応症が著しく拡大されたばかりでなく,経口投与可能のものもあり,抗生物質療法は急速に普及した。占領下の日本にも緊急輸入され,当時流行した発疹チフス,腸チフス,赤痢などの防疫に貢献し,結核,梅毒,恙虫
(つつがむし) 病などにもきわめて威力を発揮した。
52 年には
エリスロマイシン
も発見された。
抗菌性抗生物質の開発史は,別の見方をすれば,耐性菌との闘いの歴史であるともいえる。とくにブドウ球菌,腸内細菌
(赤痢,腸チフスなど),結核菌において深刻で,抗生物質が広く用いられるようになってしばらくして,高頻度で耐性菌が分離され,多剤耐性菌も出現するようになった。しかし現在では,耐性機構も詳しく研究され,耐性菌にも有効な薬剤,あるいはもともと抗生物質が効きにくい緑膿菌や変形菌にも作用する薬剤が開発されている。ペニシリンやセファロスポリンなど
βラクタム抗生物質
は細菌がつくるβ‐ラクタマーゼという酵素によってこわされるが,
6‐アミノペニシラン酸の発見 (1959)
によって,これを出発材料としてβ‐ラクタマーゼに抵抗性の,天然のペニシリン類よりすぐれた半合成ペニシリンが開発されるようになった。同様のことが
7‐アミノセファロスポラン酸を用いる半合成セファロスポリンについても行われ,現在でも半合成βラクタム抗生物質は最も広く用いられている。それ以降,いっそうすぐれた抗生物質を得る方法として,
抗生物質の半合成は,リファマイシン類,テトラサイクリン類,アミノ配糖体,マクロライド抗生物質類その他に広く用いられ成果をあげている。
梅沢浜夫は,ストレプトマイシン耐性結核菌に有効な
カナマイシン
を発見したが,カナマイシン耐性機構の研究から,リン酸転移酵素やアセチル化酵素などによる不活化機構を見いだし,これらの酵素の作用を受けない
ジベカシン
の合成に成功した。耐性機構に基づいて有効な物質を得る方法論を築いたといえる。
抗カビ抗生物質としては,
ナイスタチン
(1950),
トリコマイシン
(1951) などをはじめとして,いくつもの抗生物質が見いだされているが,毒性が高く,ほとんどが外用に限られる。抗ウイルス抗生物質も探索されているが,まだ有効なものは見いだされていない。一方,抗腫瘍抗生物質は,世界にさきがけて梅沢浜夫が実験動物腫瘍を試験法に採用し
ザルコマイシン
(1953) を発見して以来,抗腫瘍抗生物質の探索は世界的に行われるようになった。癌の治療に用いられている抗生物質も,
現在までに 10 種
ほどになり,かなりの成果をあげているが,今なお盛んに研究が行われている。
65
年ころから,微生物の生育は阻害せず動物の特定の酵素を阻害する物質
(酵素阻害剤)
の探索が梅沢浜夫らによって開拓され,新しい薬理作用を示す医薬品を微生物生産物から得る道が開かれた。
【抗生物質を生産する微生物】
抗生物質を生産するカビ,放線菌,細菌などは,ほとんど土壌から分離されている。世界中いたるところの土壌が採取され,高地あるいは海洋など人間が近づきがたい場所からも土が拾われ,菌が分離されている。純粋に分離培養された菌の一つ一つについて,
抗生物質生産の有無をいろいろな試験法で調べ
(
スクリーニング
という),有効な物質を分離精製する。現在までに得られている抗生物質のうち約
60
%が放線菌由来のものであり,治療に使用されている抗生物質の
90
%以上が放線菌によって生産されていることから,新しい放線菌の探索が今なお続けられている。放線菌は,カビと細菌のいくつかの性状を併せもつ微生物である。
抗生物質名の語尾に
〈マイシン mycin〉
がついているものが非常に多いが,これは
放線菌
Actinomycetales
に由来するものであることを示す。 抗生物質を生産する多くはバチルス属bacillusのものであり,カビではアオカビ,コウジカビなど各属のものがある。工業生産のためには,生産能の最も高い菌を選び出し,さらに,これに
X
線や紫外線照射や突然変異剤を作用させたりして,いっそう高い生産能をもつ菌に改良する。ペニシリンは現在,最初のころの菌株より数千倍の生産能をもつ菌を用いている。最近の遺伝子操作技術もまた,抗生物質の生産性の向上や新抗生物質の探索といった方面で利用研究が進められている。
【各種の抗生物質】
[抗菌性抗生物質]
細菌はグラム染色によりグラム陽性菌とグラム陰性菌に大別され,グラム陽性菌と陰性菌では,抗生物質に対する感受性,抵抗性が異なる。グラム陽性菌には,化膿性疾患を起こすブドウ球菌,溶血性連鎖球菌
(溶連菌),肺炎双球菌,炭疽菌,ジフテリア菌などがあり,グラム陰性菌には,大腸菌,赤痢菌,チフス菌,コレラ菌,緑膿菌などがある。結核菌は,抗酸性染色という染色法で区別され,抗酸菌という群に属する。
(1)
ペニシリン,セファロスポリン類 6‐アミノペニシラン酸
(6‐APA)
に化学的に任意の側鎖をつけることにより,多数の半合成ペニシリンが開発されている。そのなかには,ペニシリナーゼに安定で耐性菌に有効な誘導体やグラム陰性菌,緑膿菌に有効な抗菌スペクトルの広い誘導体あるいは経口投与可能なものなどがある。
セファロスポリン C
は,ペニシリンより酸性での安定性が高く,ペニシリナーゼにも強いことから,7‐アミノセファロスポラン酸
(7‐ACA)
を出発材料としてペニシリン類と同様にすぐれた誘導体がつぎつぎと開発され,非常に広く用いられている。
(2)
ストレプトマイシン,カナマイシン類 ワクスマンによって
1944
年に見いだされたストレプトマイシンは,とくに抗結核薬としてすぐれ,人類を結核の恐怖から救ったことで特筆される。
57
年梅沢浜夫によりストレプトマイシン耐性菌に有効なカナマイシンが発見され世界各国で使用されるようになり,さらにカナマイシン耐性菌に有効な
ジベカシン
(1971)
が耐性機構の研究に基づいて開発された。これらは構造的にアミノ配糖体抗生物質と呼ばれるが,耐性菌や緑膿菌などの不感受性菌にも有効なアミノ配糖体抗生物質がつぎつぎと開発され,現在では
ゲンタマイシン
,トブラマイシン,アミカシン,シソマイシン,フラジオマイシン
(ネオマイシン),パロモマイシンその他が臨床的に用いられている。アミノ配糖体抗生物質は,経口投与により吸収されないので注射で用いるが,強弱の差こそあれ聴力障害などの副作用を伴う。なお,抗結核薬としては,耐性菌の出現を抑え副作用を軽減する目的から,多剤併用を行うが,パス,ヒドラジドなどの合成剤に併せて,
抗生物質としてアミノ配糖体のほかに
サイクロセリン
(
オキザマイシン
),
リファンピシン
などが用いられ,耐性結核菌の問題もあまり深刻でなくなった。
(3)
クロラムフェニコール P.エールリヒにより 1947
年に発見された広範囲スペクトル抗生物質で,クロラムフェニコールの出現により,それまで治療困難だった腸チフスをはじめとする各種疾患の治療が可能となり,広く使われるようになった。しかし,まれに起こる造血器障害などの重篤な副作用のため,現在ではその使用は著しく制限されている。工業的に完全合成されるようになったはじめての抗生物質である。
(4)
テトラサイクリン類
クロルテトラサイクリン
(商品名
オーレオマイシン
),
オキシテトラサイクリン
(商品名
テラマイシン
)
が代表的なもので,グラム陽性菌および陰性菌に広範囲の抗菌スペクトルを示し,臨床的に広く使われている。通常,内服で用いられるが,静脈注射,外用もある。副作用として,胃腸障害,肝臓障害,光線過敏症
(皮膚の色素沈着など) が知られている。
(5)
バイオマイシン
フィンレー A.C.Finlay らにより 51
年報告された水溶性塩基性物質で,ストレプトマイシン耐性菌の発育も阻止する。結核菌その他の抗酸菌のみに作用するので,二次抗結核剤としてだけ用いられる。
(6)
エリスロマイシン エリトロマイシンともいう。 52
年にマクガイア J.M.McGaire
らによって発見された,構造的に大きな環状構造をもちマクロライド系に属する抗生物質。主としてグラム陽性菌およびリケッチアの発育を阻止する物質として得られた。内服で与えても吸収がよく,組織移行性が高く,副作用も少ないので,よく用いられる。秦藤樹らによって発見された
ロイコマイシン
(
キタサマイシン
),梅沢浜夫らの
ジョサマイシン
もマクロライド系に属し,
スピラマイシン
もこの系に属する。生物活性,耐性などもエリスロマイシンに類似しており,治療薬として用いられている。
(7)
コリスチン
アミノ酸のつながった環状ペプチド構造をもち,
ポリミキシン B
も類似物質。ともにバチルス属の細菌から見いだされ,グラム陰性菌にのみ有効で,とくに他の抗生物質に比べ緑膿菌に強い作用をもつことが特徴である。比較的毒性が強いが,内服,注射などで用いる。
上に述べてきた抗生物質以外で現在治療薬に用いられているおもなものには,
バシトラシン
(環状ペプチド),
グラミシジン
(鎖状ペプチド。グラム陽性菌に有効で,主として外用で用いる),
フシジン酸
(ステロイド構造。グラム陰性菌に有効で,内服,外用する),
ホスホマイシン
(グラム陽性菌および陰性菌に広い抗菌スペクトルをもち,内服あるいは注射で用いる),
ノボビオシン
(ブドウ球菌などのグラム陽性菌および一部のグラム陰性菌に有効で,内服,注射),
リンコマイシン
(グラム陽性菌に作用し,内服,注射) などがある。
[抗真菌 (抗カビ) 抗生物質]
人体のカビ疾患は,カンジダ菌の肺,肝臓などの感染による重篤な症状や,白癬
(はくせん) 菌による水虫などの皮膚疾患が知られており,とくにこれらの菌に対する有効物質が求められている。今までに見つけられているものは,毒性が強く,主として外用で用いられる。
ナイスタチン
(1947),
トリコマイシン
(細谷省吾発見,1952),
アンフォテリシン B
(1955),
ピマリシン
(1955),
ペンタマイシン
(梅沢純夫発見,1958)
などは,化学構造からポリエンマクロライド抗生物質と呼ばれる。これらは白癬菌,カンジダなどに作用するが,経口で吸収されず,注射では毒性が強い。その後,
アザロマイシン F
(1960),
バリオチン
(竹内節男,米原弘ら発見,1959),
ピロルニトリン
(有馬啓ら発見,1965)
が得られているが,白癬菌に対する外用に限られる。
(1)
グリセオフルビン
ペニシリン再発見前にイギリスでカビから分離された。内服および外用薬として用いられるが,白癬菌以外の真菌症には無効である。
(2)
トリコマイシン
腟トリコモナスに対する作用を指標として分離され,腟カンジダ症,腟トリコモナス症,白癬菌症その他の皮膚真菌症を主とし,腟錠と軟膏がつくられている。
[抗ウイルス抗生物質]
日本脳炎,狂犬病,インフルエンザその他のウイルス病に対する抗生物質も探索されているが,まだ使用できる抗生物質は見つかっていない。ウイルスだけを殺して寄生細胞には無害な物質を探す困難さがあり,またウイルス病の予防に有効なワクチンのあることにもよると思われる。
[抗腫瘍抗生物質]
癌細胞は外部から侵入した病原体と異なり正常細胞が癌化したものであって,選択的に癌細胞だけを殺す薬は得られていない。日本では,世界にさきがけて実験動物腫瘍を用いて制癌抗生物質の探索を始め,この分野では世界の水準の先端にあるといえる。日本で発見され臨床的に用いられているものに,秦藤樹の
カルチノフィリン
(1954),
マイトマイシン
(1956),梅沢浜夫の
ブレオマイシン
(1966),
ペプロマイシン
(1977),
アクラシノマイシン A
(商品名
アクラルビシン
,1977),立岡末雄の
クロモマイシン A3
(1955),石田名香雄の
ネオカルチノスタチン
(1965)
があり,とくにブレオマイシン,マイトマイシンは外国でもよく用いられている。外国で発見されたもので治療に用いられているものに,
アクチノマイシン D
,
ダウノルビシン
(商品名
ダウノマイシン
),
ドキソルビシン
(商品名
アドリアシン
)
がある。一般に,胃癌,肺癌などの内臓癌には制癌剤が効きにくいが,ドキソルビシンは各種内臓癌に効くといわれている。ドキソルビシンの心臓への毒性を軽減したものが
アクラシノマイシン A
である。熱帯植物から抽出された制癌剤
メイタンシン
は微量しか得られない欠点があるが,これの関連物質が放線菌から分離された
(
アンサマイトシン
,武田薬品工業,1979)。多量に得られる有利さがあり,微生物利用のすぐれた点を示す好例といえる。
(1)
ブレオマイシン 66
年梅沢浜夫らにより見いだされた。扁平上皮癌に著しい効果を示すものであり,ブレオマイシンの発見により,それぞれの癌に有効な薬を見つけ出す可能性を導いた。
(2)
マイトマイシン 1956
年秦藤樹らによって見いだされた。多くの同族体を含むが,このうちマイトマイシン
C
が抗腫瘍剤としてすぐれ,臨床的には白血病,肉腫などに広く使用されている。
[特異酵素阻害物質]
65
年ころから梅沢浜夫らによって新しく開拓された分野で,微生物生産物から,抗生物質的活性に基づかないで,動物の酵素を阻害する物質を探索し,新しい薬理作用をもった治療薬を得ようとするものである。そのうち,ペプシンを阻害する
ペプスタチン
は胃潰瘍,十二指腸潰瘍に有効であり,カテコールアミン類合成を阻害する
フザリン酸
は血圧降下作用をもち循環器系の病気に有望である。またアミノペプチダーゼ阻害の
ベスタチン
は,免疫系を促進する作用がある。新しい医薬品を開発するために今後ますます発展する分野といえる。
【抗生物質の作用機序】
感染症の化学療法に用いられている薬剤は,病原微生物の増殖を阻止するが,宿主の細胞への影響は少ない。これを
〈選択毒性〉
といい,化学療法の基礎概念である。それぞれの薬剤について作用機序を生化学的,分子生物学的に明らかにすることにより選択毒性を説明できることが多く,またそれに基づいて新しい薬剤を開発できる可能性がある。また作用機序の研究は,細胞分裂,生体高分子合成,エネルギー代謝など細胞の基本的機構を解明するうえでも大きな貢献をしている。ペニシリン,セファロスポリン類は,細菌の細胞壁の生合成を阻止するが,動物細胞の場合は細胞壁をもたないのですぐれた選択毒性を示す。ストレプトマイシンをはじめとする一群の抗生物質は細菌のタンパク質合成を阻害するが動物細胞のそれをほとんど阻害しないことが選択毒性のもとである。これは,タンパク質合成を行うリボソームが細菌と動物細胞とは異なっていて,
抗生物質が動物細胞のそれには結合しないことによる。このグループには,アミノ配糖体抗生物質,テトラサイクリン類,クロラムフェニコール,エリスロマイシンなどのマクロライド抗生物質,バイオマイシンが含まれる。リファンピシンは細菌細胞の
RNA
合成酵素に結合する。ナイスタチンなどのポリエン抗カビ抗生物質は,カビの細胞膜のコレステロールに作用するが,動物細胞の細胞膜にも作用するので,毒性は比較的高い。ノボビオシンは細菌の
DNA ジャイレース DNA gyrase (細菌 DNA
の二重らせんのよりをもどす酵素)
に作用する。モネンシン,サリノマイシンなどは,金属イオンとキレートをつくり,イオノフォア抗生物質と呼ばれる。細胞のエネルギー産生を阻害するアンチマイシン,オリゴマイシンなどは,選択性がなく,したがって毒性も強いが,生化学的には重要な試薬となっている。一方,臨床的に用いられている制癌抗生物質のほとんどは
DNA に結合して DNA
を切断したり核酸合成を阻害することが作用機序であるが,これらは,癌細胞のみならず分裂の盛んな正常細胞にも作用するので,癌に対する選択毒性はあまり高いとはいえず,造血器障害などの副作用が強い。有糸分裂装置に作用するビンカアルカロイドやアンサマイトシンもある。抗ウイルス剤として得られたツニカマイシン
(田村学造ら,1971)
は,細胞膜などの糖タンパク質合成を阻害する作用をもっている。
【抗生物質の副作用】
おもな副作用には次のようなものがある。
(1)
アレルギー反応 (薬剤過敏症) 代表的なものは,ペニシリンなどβラクタム抗生物質で起こるショック
(いわゆる
ペニシリンショック
) である。 1956
年東大教授尾高朝雄が歯の治療の際に用いられたペニシリン注射でショック死し,世の注目をあびた。発生頻度は低いが,重篤な場合には死に至る。使用前に皮膚反応テストを行う。経口ペニシリンも開発されたが,内服でも起こる場合もある。
(2)
感覚器および神経障害 ストレプトマイシンが結核の特効薬として登場してまもなく患者が聴神経を侵され,俗に
〈ストマイつんぼ〉
という言葉が生まれた。アミノ配糖体抗生物質やバイオマイシンは,長期の大量使用によって第
8
脳神経障害を起こす。腎臓に障害がある場合は血中濃度が高く持続するので,これらの薬剤を長期間使うときは腎臓や聴力の検査をひんぱんに行うべきである。
(3)
腎臓障害 薬剤が腎臓から排出される以上,程度の差はあるが腎臓に障害を与える抗生物質は多い。長期間使用の際には尿検査を行う。
(4)
肝臓障害 マクロライド抗生物質,テトラサイクリン,クロラムフェニコール,ノボビオシンなどは肝臓障害を起こすことがある。血液検査による肝機能検査が重要である。
(5)
造血器障害 クロラムフェニコールにより,まれに
再生不良性貧血
を起こすことがあり,致死率は高い。このため,クロラムフェニコールは使用が制限されるようになった。
(6)
胎児,新生児に対する影響 新生児にクロラムフェニコールを与えると,嘔吐,不整呼吸,虚脱などのグレー症候群を呈する。テトラサイクリンは,胎児,新生児の骨や歯に沈着し,発育を悪くすることがある。
(7)
菌交代症
口腔,上気道,消化管,腟などにはいろいろな細菌が一定の比率で住みついて生理的役割をはたしているが,
抗生物質投与により薬剤感受性の違いからこの比率がくずれ
菌交代現象
を生ずる。
ブドウ球菌腸炎
(広域抗生物質を投与中,耐性ブドウ球菌が腸管内で増殖して腸炎を起こす),
カンジダ症
(抵抗力の減じた患者に多量の抗生物質を長期にわたり使用するとカビであるカンジダ・アルビカンスCandida
albicansにより腸管カンジダ症を起こすことがある),
偽膜性腸炎
(嫌気性の耐性クロストジウムによる菌交代症腸炎で,発熱,腹痛,下痢を呈し死に至ることもある)
などが知られている。
(8)
抗腫瘍抗生物質による副作用 現在用いられている制癌剤は,細胞分裂の盛んな正常組織にも作用するので,宿命的に白血球減少,免疫力低下,胃腸障害,脱毛などの副作用を伴う。ブレオマイシンは,骨髄にはあまり分布せず骨髄障害は低いが,
肺繊維症
を起こすことがある。肺毒性の低いペプロマイシンが開発された。ドキソルビシンなどのアントラサイクリン系抗生物質は心臓毒性をもつことが特徴的である。最近,心臓毒性の少ないアクラルビシンが開発された。
⇒化学療法‖細菌
鈴木 日出夫
【農薬,獣医畜産への抗生物質の利用】
主要作物の病害防除の目的で新抗生物質を探究したのは日本が最初である。イネのいもち病は
1 種のカビによって起こる。 1950
年代までは,いもち病の防除剤として,有機水銀剤が広く用いられていた。しかし,この残留性と慢性毒性が問題となり,また環境汚染などの問題も加わって利用できなくなり,新薬の開発が求められた。これが契機となって,ブラストサイジン
S (住木諭介ら,1958),カスガマイシン (梅沢浜夫ら,1965)
が開発された。そのほかイネの白葉枯病に対するセロサイジン
(住木諭介ら,1958),イネの紋枯病に対するバリダマイシン
(武田薬品工業,1971),モモの黒斑病とリンゴの斑点葉枯病などに対するポリオキシン
(鈴木三郎ら,1958),うどんこ病に有効なミルディオマイシン
(武田薬品工業,1983)
などがある。医薬として開発されたストレプトマイシン,オキシテトラサイクリンなども農薬用抗生物質として登録されている。家畜,家禽の感染症に対しては,医薬品と同じ抗生物質も使用されるが,ヒトへの影響,耐性菌出現の問題から,動物専用の抗生物質の開発が盛んである。動物に使用した場合,食用に供される肉,乳,卵などに残留しないよう,抗生物質ごとに使用する動物の発育期,出荷前の使用禁止期間が決められている。動物専用としては,細菌感染を対象とするチロシジン
(1961),チオストレプトン (1955),腸内寄生虫の予防と治療にハイグロマイシン
B (1958),デストマイシン A (1965),コクシジウム症用のモネンシン
(1967),サリノマイシン (1974)
などがある。経口的に長期投与を行っても副作用の少ない抗生物質が飼料に添加され,家畜の発育促進に用いられる。病気に対する抵抗性を高め死亡率を減少させるほか,腸内の有害菌の発育を抑え有用菌の繁殖を促す作用があると考えられている。人畜共通の抗生物質もあるが,チオペプチン
(1970),マカルボマイシン (1970)
などが動物専用である。
鈴木 日出夫
高橋 信孝
|
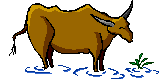
 welcome堆肥屋com
へ
welcome堆肥屋com
へ 